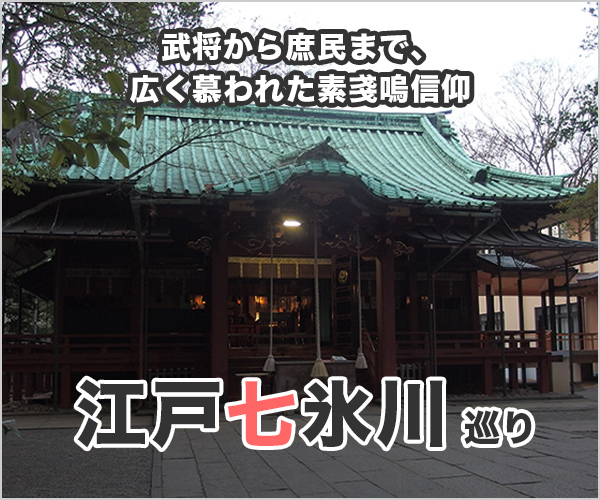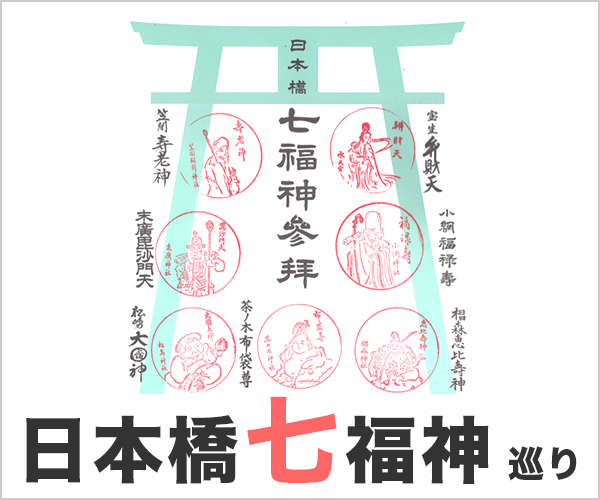柳原稲荷神社(足立区柳原)
2025.07.16[ 神社 ]

徳川家康が江戸城の鬼門除けのために創建したと伝わる「柳原稲荷神社(足立区柳原)」。
創建年代については諸説あるようですが、社伝によれば、1606年(慶長11年)この地を訪れた徳川家康が、柳が青々と繁っていて神聖な場所と感じたため、江戸城の鬼門除けとして創建を指示した、という逸話が残っているそうです。1786年(天明6年)に洪水で社殿が流失しましたが、1794年(寛政6年)に再建されました。
東京都足立区教育委員会による案内板『柳原稲荷神社』には、以下のように記されています。
==========
当社の創建は詳らかではないが、『葛西誌』に「慶長四年(一五九九)の鎮守と云」とある。しかし、柳原村は、元禄年間(一六八八~一七〇四)に葛西郡小谷野柳原村より分村独立しているので、それ以降に村の鎮守として祀られたものであろう。江戸期にあっては同じ柳原の理性院持ちであった。
祭神は、宇迦之御魂神。明治十二年(一八七九)の東京府神社明細簿によると、本社殿、拝殿、境内二百三十五坪(官有地)とあり、境内社として、高木神社(産霊神)と日枝神社(大山咋神・東照宮)の二社があり、氏子は三十五戸と記されている。
高木神社は江戸期の第六天社で、神仏混淆を禁止された明治以降に改称した。また、明治四十四年(一九一一)に日枝神社は高木神社に合祀された。
昭和八年(一九三三)、柳原富士講により浅間神社が勧請され、富士塚が築かれた。これは、昭和五十九年(一九八四)十一月、足立区登録有形民俗文化財となった。講中による七富士巡りなどが行われている。
また、当社に奉納される柳原箕輪囃子は、江戸期より伝わる民俗芸能で、昭和五十七年(一九八二)十二月、足立区登録無形民俗文化財となった。
令和二年三月
東京都足立区教育委員会
==========
上記の通り、御祭神は宇迦之御魂神。
最寄駅は、東武鉄道伊勢崎線「牛田」駅、あるいは京成本線「京成関屋」駅。各線「北千住」駅からだと、徒歩約10分ちょっと。

神社外観。

正面の鳥居。

拝殿。

拝殿の横にあるのは境内社の浅間神社の鳥居。

鳥居の先には富士塚があります。

こちらは境内社の高木神社。江戸時代には第六天社(第六天神)と呼ばれていました。明治期に日枝神社を合祀しています。

境内の石碑・石塔。

リンク
MAP
東京都足立区柳原2丁目38−1