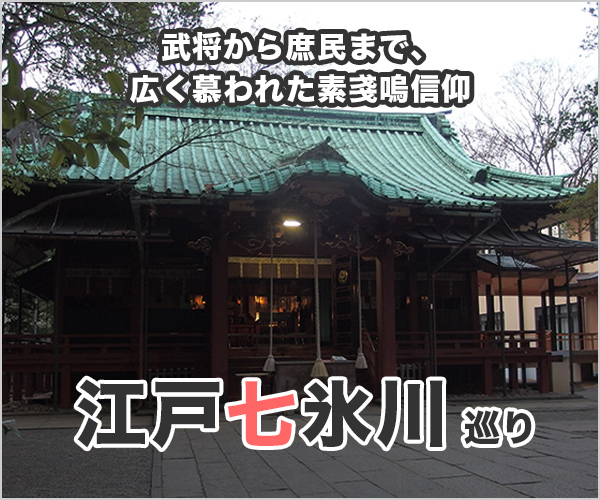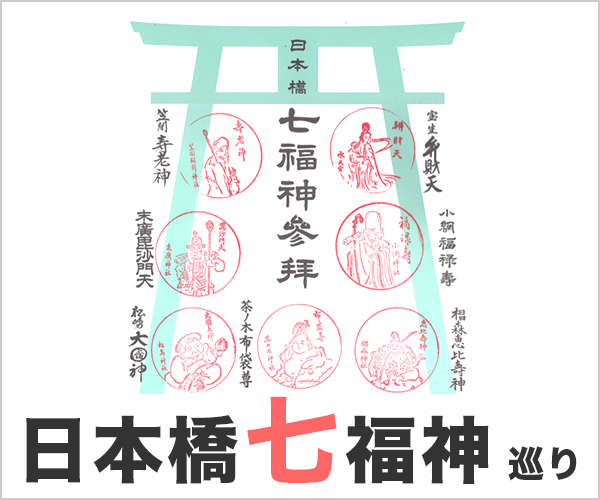千住神社(足立区千住宮元町)
2025.08.05[ 神社 ]

かつては「二ツ森」と呼ばれていた「千住神社(足立区千住宮元町)」。
平安時代の926年(延長2年)に創建された稲荷神社と、鎌倉時代の1279年(永承6年)に創建された氷川神社が起源と伝わっています。鬱蒼と繁った林の中にふたつの神社があったことから、「二ツ森」と呼ばれていたと云います。そして1873年(明治6年)に稲荷神社を氷川神社に合祀し「西森神社」となり、さらに1915年(大正4年)に現在の「千住神社」に改称されました。
境内にある『由緒』碑には、以下のように記されています。
==========
当神社は、千住に集落が形成され始めた、延長四年(九二六年) 土地鎮護と五穀豊饒を祈って、伏見稲荷より御分霊を勧請し、稲荷神社を創立した。永承六年(一〇五一年)源義家は、奥州征伐の際、荒川(現千住大橋付近)を渡り、二ツ森(千住神社)に陣営し、神前に戦勝を祈願したと、古記録に記載されている。
弘安二年(一二七九年)に武蔵国、一の宮氷川神社の御分霊を勧請し、氷川神社を創立した。この為に、鎌倉時代より江戸時代には、ここを二ツ森と言っており、旧考録には、代々の将軍が、鷹狩りを行ったという記事が、随所に記録されている。
寛永年間に至って、千住が日光街道の第一宿となり、当神社は、その西方にある為に、西の森とも言われた。江戸時代までは、稲荷神社と氷川神社の二つの神社があったが、明治五年十一月十八日、両社は、村社と定められ、更に翌六年六月には、稲荷神社を氷川神社に合祀し、西森神社と名を改めた。同年七月五日に、足立区内最高雅一の御社と定められ、更に大正四年十二月十五日以来、千住神社と改称した。
昭和二十年四月、戦災にあい、全ての建物は焼失したが、三十三年以降、御社殿、社務所、会館、等が再建され、戦前以上に立派に整備された。
==========
御祭神は、須佐之男命・宇迦之御魂命。また現在は千住七福神のひとつとして「恵比寿神」がお祀りされています。
最寄駅は、各線「北千住」駅。徒歩約15分ほど。

参道の一ノ鳥居。参道には合計三つの鳥居があります。

こちらは三つ目の鳥居。

拝殿。

境内社の経王稲荷社。

境内社の火伏せ三社。

境内社の天満宮。

千住七福神「恵比寿神」。

境内社の稲荷社。

千住富士(富士塚)。

御由緒の刻まれた石碑。
リンク
MAP
東京都足立区千住宮元町24−1