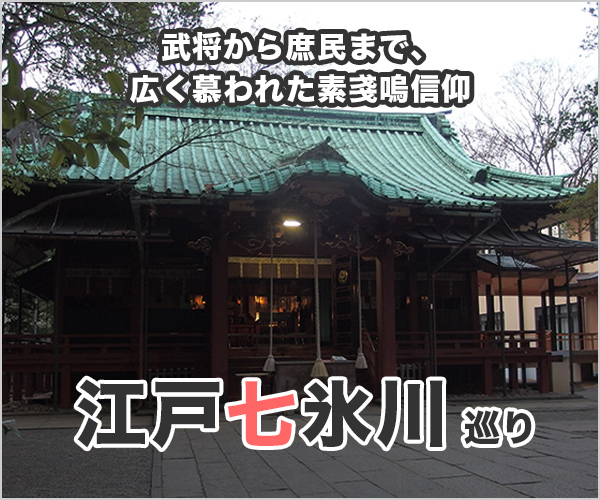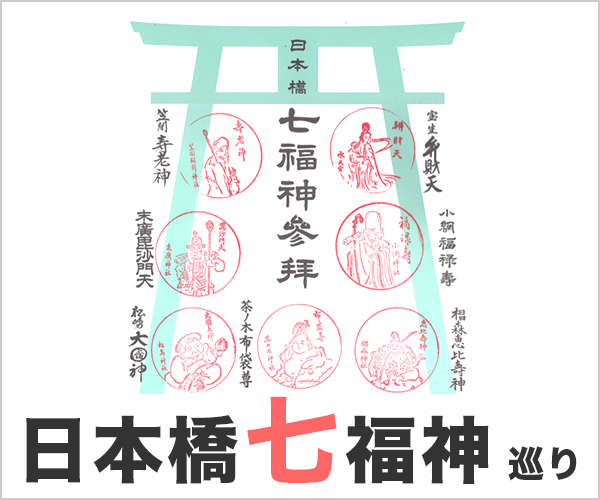大宮前春日神社(杉並区宮前)
2025.02.03[ 神社 ]

江戸時代創建・新田開拓の成功を祈願して奉斎された「大宮前春日神社(杉並区宮前)」。
江戸時代前期の1658年(万治元年)頃に、新田開拓の成功を祈願して奉斎され、そして新しく出来た大宮前新田村の鎮守としてお祀りされてきました。
杉並区教育委員会による案内板には、以下のように記されています。
==========
当社は旧大宮前新田村の鎮守で、祭神は武甕槌命・経津主神・天児屋根命・毘売命の 4柱です。当社は大宮前新田村が開村した万治年間(1658~1660)に、井口八郎右衛門の勧請によって創建されたと伝えられています。「新編武蔵風土記稿」には「除地二段五畝六歩 小名本村ニアリ 神体八木ノ坐像長五寸許 太神宮八幡ヲ相ニス 木ノ坐像各長五寸許 覆屋一間半四方 内ニ小祠ヲ置 拝殿四間ニ二間南向ナリ 社前二鳥居ヲ立石燈籠両基ヲ置 当村ノ鎮守ニシテ例祭ハ十月廿二日ニ修ス 慈宏寺持」とあります。明治5(1872)年11月には村社となりました。本殿は明治21(1888)年、拝殿は明治10(1877)年の建築です。
境内の石燈籠一対は元文元(1736)年11月の造立で、石造神鹿一対は明治27(1894)年4月に、石造神狐一対は明治33(1900)年4月に氏子が奉納したものです。社殿前の「大宮前鎮守」の石碑は、この地域の地名変更に伴って「大宮前」の地名を後世に伝えるために造立されたといわれています。
また当社では、下高井戸八幡神社の宮司斉藤近大夫(文政5(1822)年生)の指導によると伝えられる「大宮前囃子」(杉並区登録無形民俗文化財)が、例祭日に奉納されています。
境内末社には、第六天神社・御嶽神社・稲荷神社があります。
==========
御祭神は、武甕槌命・経津主神・天児屋根命・毘売命。
現在は下高井戸八幡神社の兼務社となっているようです。
最寄駅は、京王電鉄井の頭線「富士見ヶ丘」駅。徒歩約15分ほど。

五日市街道からの神社外観。

正面の鳥居。

鳥居の扁額。

拝殿。

参道にある、天を向いている狛犬。明治期に奉納されたもの。

境内社。左から、第六天、稲荷社、さらに別に右にあるのが三峯神社。

杉並区教育委員会による案内板。

境内の様子。
MAP
東京都杉並区宮前3丁目1−2