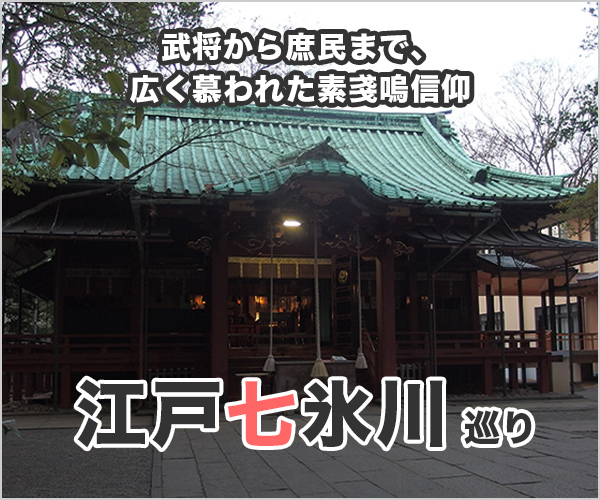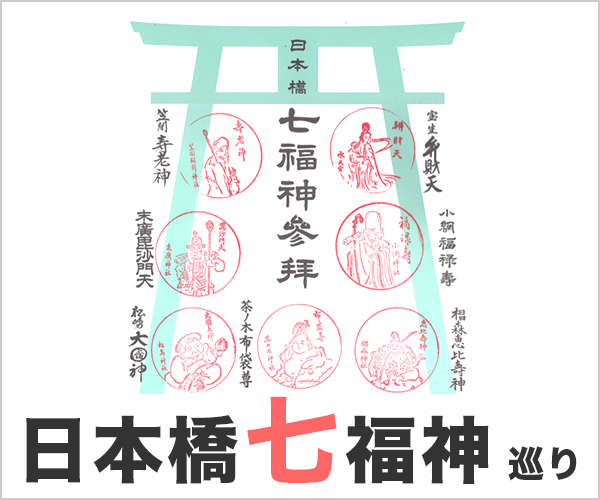神明天祖神社(杉並区南荻窪)
2025.02.04[ 神社 ]

旧上荻窪村の鎮守神としてお祀りされていた「神明天祖神社(杉並区南荻窪)」。
詳しい創建年代は不明ですが、1584年(天正12年)の検地の時には既に小祠があったということから、それ以前に創建されたものと思われます。江戸時代には上荻窪村の鎮守となっていましたが、明治期に荻窪八幡神社の境外摂社となりました。「神明天祖神社」のほか、「南荻窪天祖神社」とも呼ばれているそうです。
境内に掲示されている『天祖神社由緒』には、以下のように記されています。
==========
当神社がいつ頃創建されたか詳かでないが、天正十二年(三百八十年前)に伊賀の人小林大弁・浅沼田島等命を受けて、”検地”をした時既に草むらの中に小きな社があったということであるからこれ以前に創建されたものであろう。その後伊賀の百姓等がこの附近に移り住んで社を修め、伊勢大明神と崇め祀って来たものと傳えられている。
天正十八年下総国香取郡水戸谷の城主であった水戸谷蔵人景賢が小田原の北条氏に加担して湯本口の戦で豊臣勢に破れ、氏族散乱して各地に流浪した。景賢の子景正姓を三刀谷と改めて武州に入りその孫伴蔵正近、元和年中に多摩郡荻久保村に居住し、紀州公に仕え、この地に広大な邸宅を構え、多くの土地を私有するに及んで荒廃した林中に「伊勢の宮」のあることを知って之を改修し祭儀を修め四圍に櫻樹を植えて「櫻の馬場」と呼んだ。社の東方一帯の地は其の跡で寛永の頃(三百三十〜四十年前)紀州公お鷹狩りの節のお休憩所にあてられたと伝えられている。
三刀谷氏其の後姓を井川と改め代々この土地に居住され、当主俊之助氏は景賢より第十五代目の子孫に当る。
文政元年(百五十二年前)村内百姓当麻六左衛門梅田紋次郎等四圍を拓き翌二年七月百姓長澤治兵衛周囲に植林した。
社は井川氏の管理から村人に移り一時村内「光明院」の持分となったが更に上荻八幡神社の境外摂社として存続し、大正五年御大典を記念して村民一同境内に植林し、昭和九年・社務所を同三十二年・御社殿及び神楽殿を新築した。
壱千八百余坪の神域は附近住民の憩いの森として親しまれて現在に至っている。
昭和四十五年拾月吉日
==========
御祭神は、天照大御神。
最寄駅は、中央本線「荻窪」駅、あるいは「西荻窪」駅。どちらからも徒歩約15分ほど。

神社外観。神社敷地の西側からの眺め。

西側入口にある一ノ鳥居。

参道の途中にあるニノ鳥居。

拝殿前にある三ノ鳥居。

拝殿前の狛犬。

拝殿。

境内社の御嶽神社。

御由緒板。

杉並区教育委員会による案内板。

MAP
東京都杉並区南荻窪2丁目37−22