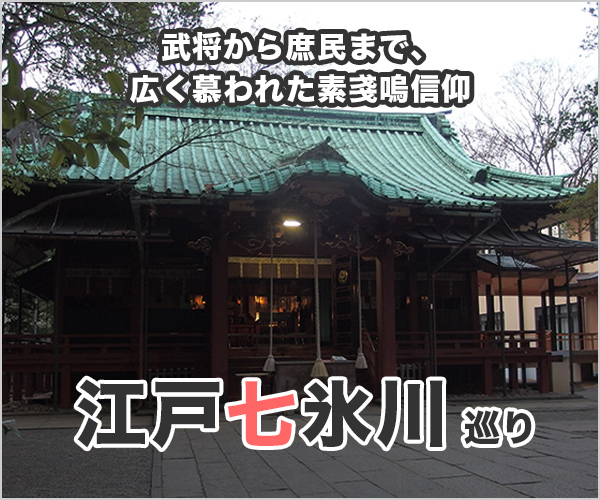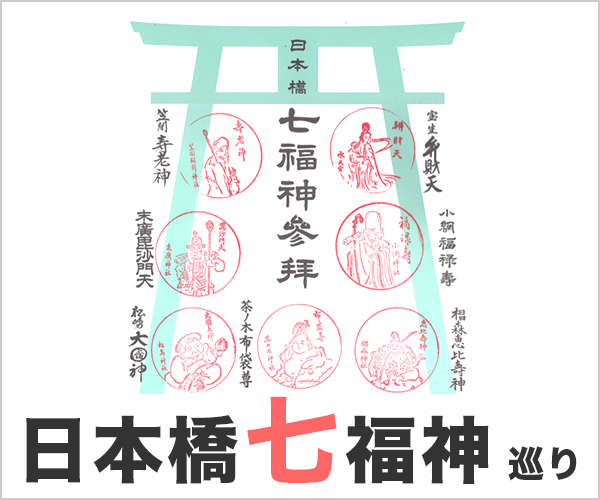本村神社(府中市押立町)
2025.04.08[ 神社 ]

押立村本村地区の鎮守神
本村神社(府中市押立町)
江戸時代創建・押立村本村地区の鎮守としてお祀りされた「本村神社(府中市押立町)」。
江戸時代前期の万治年間(1658年〜1661年)にあった多摩川の洪水に伴う流路変更により押立村が分断された後に、本村地区の鎮守として祀られた天王社が起源と伝わっています。
境内にある案内板には、以下のように記されています。
==========
神社名本村神社(旧称天王さま)
江戸時代初期、多摩川の流路が変わり、村が南北に分断され、北岸が本村(現在の府中市押立町)、南岸が向押立(現在の稲城市押立)と呼ばれるようになった後創建されたと思われるが、由緒は詳らかではない。
御祭神は、天照皇大神、稲蒼魂命、素戔嗚尊の三柱の神々です。
天照皇大神は八百万の神々の中でも最も尊い神、又日本の総氏神様として、私たちの生活を見守って下さる神として信仰されています。
稲蒼魂命は稲霊で、我々の生命の源である食物を司る神、農業の守護神、商売繁盛の神として信仰されています。
素戔鳴尊は、別名を牛頭天王といい昔から天王さまと一般に称されています。八岐大蛇を退治した神と知られ、その強い力で疫神や疫病をはらい退けて下さる神として信仰されています。
例祭は七月、海の日に近い土日に斎行されます。特殊神事として、神輿の渡御の儀が行われ、神主が氏子の家々をお祓いしてまわります。
==========
御祭神は、天照皇大神・稲蒼魂命・素戔嗚尊。
現在は押立神社の兼務社となっているようです。
最寄駅は、京王電鉄京王線「飛田給」駅。徒歩約15分ほど。

正面から。

境内社。

境内の案内板。

押立の渡しへと続く、いわゆる「渡船場道」側からの外観。
リンク
MAP
東京都府中市押立町4丁目35−3