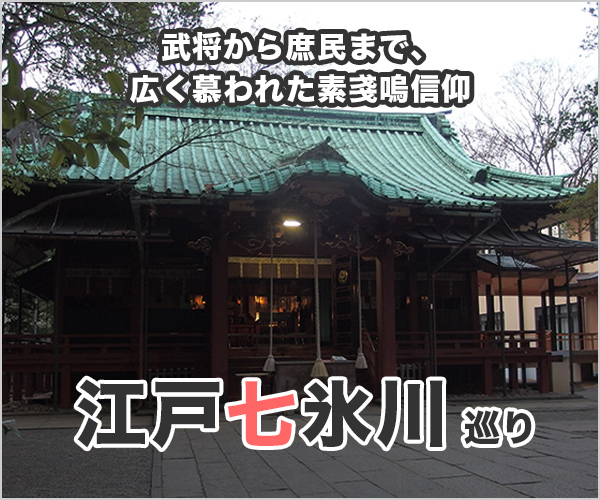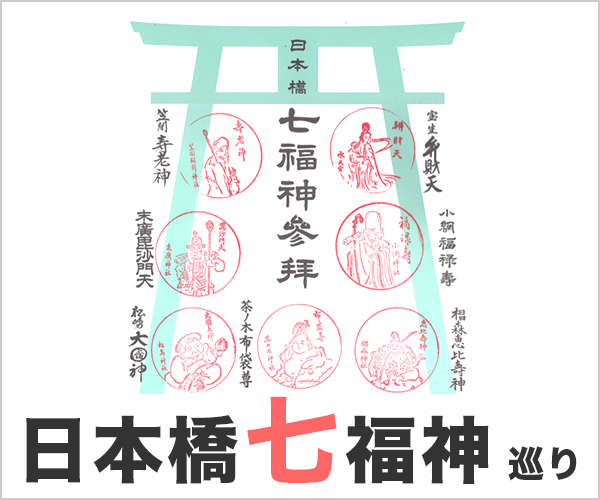府中熊野神社(府中市西府町)
2025.02.19[ 神社 ]

江戸時代には旧本宿村の総鎮守としてお祀りされていた「府中熊野神社(府中市西府町)」。
江戸時代初期の創建と伝わっています。創建当初は現在の府中第五小学校の辺りにあったそうですが、1777年(安永6年)に現在地に遷座しました。江戸時代には旧本宿村の総鎮守としてお祀りされていました。
境内にある石碑に刻まれた『由緒』には、以下のように記されています。
==========
當神社は往古「熊野大権現」と称され旧本宿村の総鎮守てあった。
その創建は江戸初期と伝えられ、当時境内に別当寺である弥勒寺が勧請されており当地にも熊野信仰伝播の様が見られ神仏習合の信仰形態が調っていた。
本殿は往時の儘現存し拝殿は天保九年(一八三八)九月改築との棟札があり、拝殿内には江戸時代後期の漢詩人「江山翁大窪行」揮毫の「熊野大権現」と記した額が殿内にある。古墳裏正面には「天明八戌申歳九月吉祥日 當村氏子中願主 松本氏」と刻まれた鳥居があり、正北から境内を守護している。
宮司 記
==========
現在の御祭神は、素盞嗚命。
社殿のすぐ後ろに国史跡「武蔵府中熊野神社古墳」があります。しかし長い間古墳とは認識されておらず、最近まで「神社境内にある小山」として扱われていたそう。本格的な発掘調査は2003年から行われ、2005年に国の史跡に指定されました。
最寄駅は、JR南武線「西府」駅。徒歩約5分ちょっと。

甲州街道から見た、神社正面。社標と狛犬、鳥居が見えます。

鳥居をくぐると、拝殿に向かってまっすぐ参道が続いています。

拝殿。

御由緒の刻まれた石碑。

境内社。

社殿の後ろ(北側)にあるこちらが国史跡「武蔵府中熊野神社古墳」。7世紀中葉から後半にかけての造営と推定されています。府中市による案内板には、以下のように記されています(一部抜粋)。
==========
武蔵府中熊野神社古墳の概要
■飛鳥時代の上円下方墳
本古墳は、7世紀の中頃の飛鳥時代に築造された、上が丸く、下が四角い上円下方墳です。古代の中国では、天はドームのような半球形で、大地は四角いものと信じられていました。この考えを「天円地方」といいますが、このような宇宙観や思想を背景として築造されたと考えられています。
■方角
古墳の中心線は、真北より約7度西へ向いていますが、古墳の築造にあたって方角を意識していたものと考えられます。
■古墳の大きさ
墳丘の規模は、3段目の上部の直径約16m、2段目の下方部の一辺約 23m、1段目の下方部の一辺約32mを測ります。墳丘の高さは、3段目の墳頂で約 6mあります。墳丘全体の中心は、石室の一番奥の部屋(玄室)の中心に合わせるように設計されていました。
■埋葬された人物
武蔵府中熊野神社古墳が、全国でも類例の少ない上円下方という墳形の古墳であることや、副葬品の質の高さから、その被葬著(理葬された人物)はおそらく東国の有力者であったと考えられます。残念ながらその人物名は、当時の文献や記録、古墳出土品に名前を記したものがないためわかりません。
==========
上円下方墳は、こちらを含めて全国で5例しかなく、とても珍しい墳形なのだそう。上記の通り被葬著は不明ですが、築造の時期を考慮すると、武蔵国府がこの地(府中)に設置されたことに大きな役割を果たした人物ではないかと考えられているようです。

鳥居の脇にある、武蔵府中熊野神社古墳展示館。

拝殿脇からの境内の眺め。
リンク
MAP
東京都府中市西府町2丁目9−5