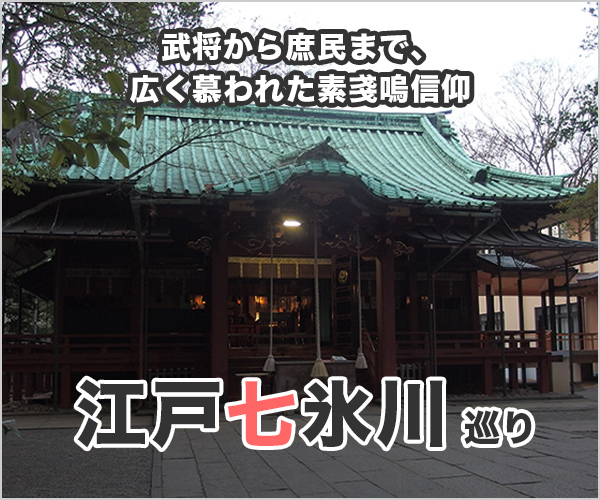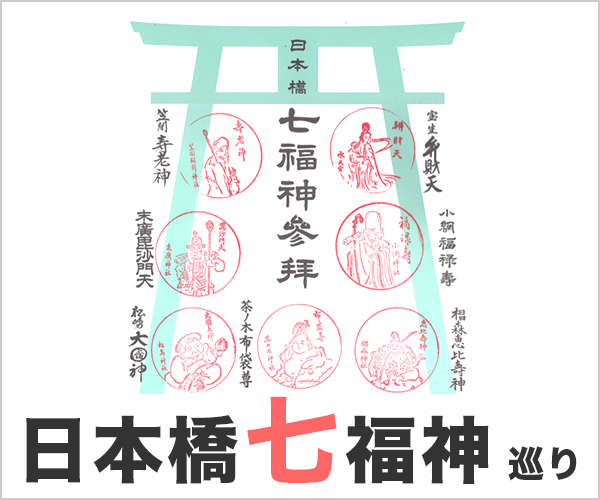鵠沼皇大神宮(藤沢市鵠沼神明)
2025.10.21[ 神社 ]

相模国土甘郷総社・大庭御厨の総鎮守としてお祀りされていた「鵠沼皇大神宮(藤沢市鵠沼神明)」。
創建年代は不明ですが、832年(天長9年)に神明宮の社殿が造立されました。烏(カラス)が多くいたことから、「烏森神社」とも呼ばれていたと云います。その後まもなく相模国土甘郷の総社となりました。また、鎌倉権五郎景政が大庭荘を伊勢神宮に寄進、大庭御厨となった以降は大庭御厨の総鎮守に定められたと伝わっています。
神社頒布の栞には、御由緒について以下のように記されています。
==========
第五十三代淳和天皇の御代、天長九年(八三二年)御社殿造立の記録があり、勧請の時期は更にどれほど遡るべきか詳らかではないが、創建の極めて古いことは明らかである。天喜三年(一〇五五年)、元亨二年(一三二二年)、天正十三年(一五八五年)、昭和六十年(一九八五年)と造営を重ねられている。
第六十代醍醐天皇の御代、延喜式が選進されたころに、奈良時代以来現在の藤沢市の内、藤沢、西富、大鋸、鵠沼、辻堂などの各地を合わせてとなえられていた相模国土甘郷の総社に列せられ、この時以来、相模国土甘郷総社神明宮と称し、あまねく人士の尊崇を集めることとなった。
又、長治元年(一一〇四年)に到って鎌倉権五郎景政が所領の大庭荘を伊勢神宮に御厨として寄進したので大庭荘が大庭御厨と呼ばれるようになってからは、境川と小出川とに挟まれた広大な伊勢神領大庭御厨総鎮守と定められ更にあつく崇敬されることとなった。
これより先、天喜年間、八幡太郎義家、奥州鎮撫の途次祈願奉幣あり。また、寿永三年(一一八四年)那須与一宗高は屋島にて扇の的を射た弓一張と残りの矢を奉納、併せて所領の那須野百石を寄進した。その後に至り明和二年(一七六五年)六月十七日領主布施孫兵衛尉頼路、参篭し祈願奉幣あり。且つ天照皇大神宮と謹書した白絹御戸張を奉納、明治維新まで例年奉幣を怠りなく続けられた。
明治元年九月、征東大総督一品中務卿有栖川宮殿下東下の際、神明宮の御染筆を賜わる。また、例祭は八月十七日。当日九基の盛装した人形山車の参進は特筆すべき盛観で、神奈川の民族芸能として県の指定があり、更に例祭そのものが「神奈川のおまつり五十選」に選定されている。
==========
御祭神は、主祭神として天照皇大神。合祀神として相殿に天手力男命・天太玉命・天児屋根命・天宇受売命・石凝刀売命。
現在境内末社としてお祀りされている「石楯尾神社」は、皇大神宮の社殿が造立される前からこの地に鎮座していたと伝わっています。つまり、石楯尾神社の鎮座地に神明宮が造られた、ということのようです。石楯尾神社には石楯尾大神・八幡大神・春日大神がお祀りされており、(皇大神宮の御祭神と)「御同座」ということになっています。
最寄駅は、小田急江ノ島線「藤沢本町」駅。徒歩約10〜15分ほど。

南側(南西)にある一ノ鳥居。

こちらはニノ鳥居。その東側にも入口があります。そしてその先には三ノ鳥居が見えます。

三ノ鳥居の先の境内の眺め。拝殿前で参道が折れ曲がっています。

拝殿。

拝殿左側には、境内社がお祀りされています。

拝殿のお隣にお祀りされているのは、もともとこの地にお祀りされていたと伝わる石盾尾神社。石盾尾神社は相模国延喜式内社十三社の内の一社で、現在では神奈川県以外には存在していない地域固有の信仰。県内で現在もその名のまま残っているのは4社のみで、こちらはそのうちのひとつ。

境内社。右は伊勢宮、左は稲荷神社。

境内社の石ノ神社。経津主神・武甕槌神がお祀りされています。

境内社。右は豊受稲荷神社、左は山王社。

境内社。右は恵比須ノ宮、左は豊受ノ宮。

こちらはニノ鳥居と三ノ鳥居の間にお祀りされている境内社の厳島神社。
リンク
MAP
神奈川県藤沢市鵠沼神明2丁目11−5