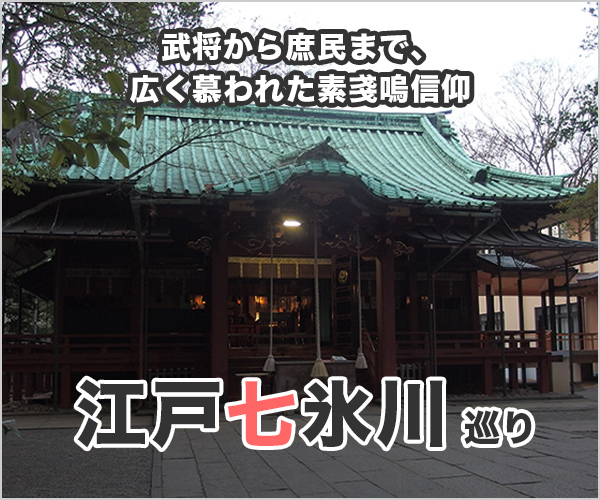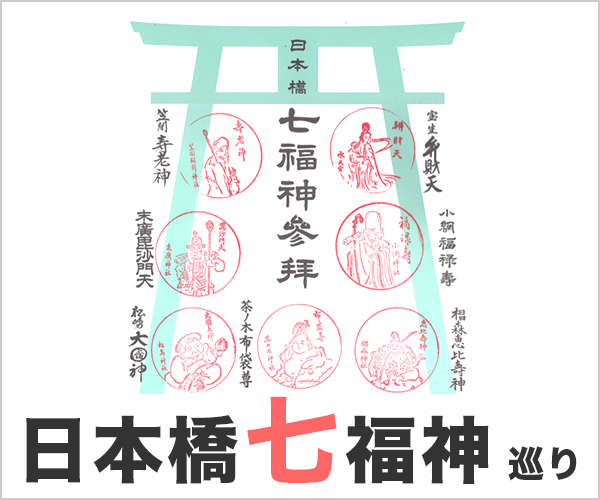西高井戸松庵稲荷神社(杉並区松庵)
2025.02.02[ 神社 ]

旧松庵村の鎮守神が起源の「西高井戸松庵稲荷神社(杉並区松庵)」。
江戸時代前期の万治年間(1658年~1660年)に開墾されたと云われる旧武蔵国多摩郡松庵村。松庵稲荷は村の鎮守としてお祀りされていました。その後1934年(昭和9年)に中高井戸村の鎮守だった稲荷社を合祀し、現在の「西高井戸松庵稲荷神社」となりました。
杉並区教育委員会による案内板には、以下のように記されています。
==========
社は旧松庵村の鎮守で祭神は受持命です。
松庵村は万治年間(1658~1660)に松庵という医者が開いたと伝えられ、安養寺(武蔵野市)の供養塔にある荻野松庵がその人ともいわれています。
境内入口には元禄3(1690)年、元禄6(1693)年銘の庚申塔があり、元禄3年のものには「武州野方領松庵新田」と刻まれています。このことから元禄3年以前には松庵村が開村していたことが分かります。
また当社は、明治維新の際に廃寺となった円光寺(天台宗・江戸八丁堀湊町普門院末)の境内にあった社で「新編武蔵風土記稿」の松庵稲荷の項には「上屋二間ニ二半 内ニ小祠ヲ置 社前ニ鳥居ヲ立 村内ノ鎮守ニシテ例祭ハ其日ヲ定メズ」と記されています。
昭和9(1934)年、隣村中高井戸村の鎮守稲荷神社を合祀以後、西高井戸松庵稲荷神社と称し、同10(1935)年には社殿を改築し、今日にいたっています。
社前の五日市街道は江戸時代には「青梅街道脇道」とも呼ばれ、木炭をはじめとする生活物資の輸送に大きな役割をはたしてきました。
なお、神社の北側裏手には、円光寺初代住職である寿海(元禄9(1696)年遷化)の墓地をはじめ、歴住の墓地や五輪塔があります。
==========
上記の通り、御祭神は受持命。
現在は下高井戸八幡神社の兼務社となっているようです。
最寄駅は、中央本線「西荻窪」駅。徒歩約15分ほど。

表通り(五日市街道)から見た神社外観。

入口にある鳥居。

入ってすぐ左手にある『狐のミイラの小祠』。高井戸八幡神社公式ホームページに説明がありました。
==========
昔、当稲荷神社の西側に円光寺と言う寺がありました。そばに大きな築山がありまして、 狐が穴を掘って小狐を育てていましたが、お寺が廃寺となり、明治30年頃、築山を取り去りましたので、親狐は子狐と別れる悲しみのあまり、前足をくわえたままの姿で拝殿の床下から発見されました。
昭和9年に西高井戸・松庵両稲荷神社を合祀するに当り、本殿を造営し、さらに昭和36年末社を建て、古来からお稲荷様のお使い姫と言い伝えられるこのお狐様をおさめてお祀りしております。
==========
(以上、下高井戸八幡神社公式ホームページより一部抜粋)

拝殿前の鳥居。その手前には、二対のお狐様が。

拝殿。

杉並区教育委員会による案内板。

庚申塔。

境内の様子。
MAP
東京都杉並区松庵3丁目10−3